乳腺外科
エビデンスに基づく最新治療と国際共同治験の提供
診療内容・得意分野
乳腺センターを設置し、手術、薬物療法、乳房再建、遺伝性乳がんへの対応を4診療科(乳腺外科・腫瘍血液内科・形成外科・遺伝子診療科)によるチーム医療を実践しています。当科は常勤医4名体制ですが、千葉大学医学部付属病院の非常勤医師の協力の下、診療と教育の両面で専門性の高い医療を提供しています。
アピールポイント
1. 専門医による迅速かつ正確な診断体制
外来各室に超音波装置を配備し、受診当日の超音波検査に加え、その場で細胞診・針生検を実施しています。初診から2週間以内に造影CTやMRIを実施し治療方針を提示することが可能です。
2. 個別化治療の推進:温存術から術前化学療法、再建まで
造影MRIによる精密評価により乳房温存術の適応を決定。3cm以上の腫瘍でも術前化学療法後に温存が可能な場合は選択肢とします。乳房切除術後の再建希望には形成外科と連携し、一期再建を積極的に行っています。
3. 広告可能な資格配置状況と新規治療への取り組み
日本乳癌学会専門医3名、日本臨床細胞学会専門医1名、がん薬物療法専門医1名、日本超音波医学会専門医2名を擁し、診療と教育の両面で専門性の高い医療を提供しています。
また、新規開発未承認薬を用いた企業及び医師主導治験を多数実施し、患者さんにより多くの治療選択肢を提供しています。
4. その他の診療体制
1)術前化学療法による腋窩郭清手術の省略
N1症例に対する術前化学療法後もセンチネルリンパ節生検を実施し、転移が消失した場合には腋窩郭清を省略、QOL向上に努めています。
2)遺伝カウンセリングと予防的手術
臨床遺伝専門医が、カウンセリングを行います。NCCNガイドラインをもとに遺伝学的検査(2020年4月より保険適応)を行い、遺伝性乳癌卵巣癌症候群が判明した場合は、予防的卵巣卵管切除術及び予防的反対側乳房切除や適切なサーベイランスを提案しています。なお、予防的反対側乳房切除は千葉大学医学部付属病院などの日本遺伝性乳癌卵巣癌総合診療制度機構が定める認定施設へ依頼しています。
3)地域連携クリティカルパス
術後経過観察を地域の医療機関と連携して行い、患者の負担軽減と医療の質の均一化を図っています。登録者は4,000名を超え、再発疑い時には迅速な逆紹介が可能な体制を整備しています。
医療機関の皆様へ
近年、術前術後の手術期治療や再発治療において免疫チェックポイント阻害剤や薬物抗体複合体などの新規薬剤が保険承認されました。現在も新たな薬剤の企業治験が進行中です。乳癌領域で開発中の治験の多くに当施設は参加しており患者さんにより多くの治療選択肢を提供しています。
医師のご紹介
乳腺外科部長
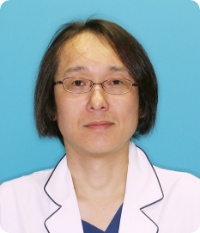
中村 力也(なかむら りきや)
【指導医、専門医、認定医など】
- 日本外科学会 認定医・専門医
- 日本乳癌学会 認定医・専門医・指導医
- 日本臨床細胞学会 専門医
- 日本超音波学会 専門医
【専門分野/得意分野】
- 乳がんの診断、治療
医長
羽山 晶子(はやま しょうこ)
【指導医、専門医、認定医など】
- 日本外科学会 専門医
- 日本乳癌学会 認定医・専門医
- 日本超音波医学会 専門医
- 日本臨床腫瘍学会 がん薬物療法専門医
- マンモグラフィー検診精度管理中央委員会認定読影医
【専門分野/得意分野】
- 専門は乳がんの診断、手術、再発治療
医員
山田 英幸(やまだ ひでゆき)
【指導医、専門医、認定医など】
- 日本外科学会 認定医・専門医
- 日本乳癌学会 認定医
- マンモグラフィー検診精度管理中央委員会認定読影医
【専門分野/得意分野】
- 専門分野は乳がんの診断、手術、術前術後治療、再発治療
医員
佐久間 結(さくま ゆい)
【指導医、専門医、認定医など】
【専門分野/得意分野】
非常勤医師
寺中 亮太郎 (てらなか りょうたろう)
【指導医、専門医、認定医など】
- 日本外科学会 認定医・専門医
- 日本乳癌学会 認定医・専門医
- マンモグラフィー検診精度管理中央委員会認定読影医
【専門分野/得意分野】
- 専門分野は乳がんの診断、手術、術前術後治療、再発治療
非常勤医師
吉村 悟志(よしむら さとし)
【指導医、専門医、認定医など】
- 日本外科学会 認定医・専門医
- 日本乳癌学会 認定医
- マンモグラフィー検診精度管理中央委員会認定読影医
【専門分野/得意分野】
- 専門分野は乳がんの診断、手術、術前術後治療、再発治療
非常勤医師
山本 寛人 (やまもと ひろと)
【指導医、専門医、認定医など】
【専門分野/得意分野】