ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 健康づくり・病気予防 > 栄養 > 県民の元気を応援するお店「健康ちば協力店」 > メニューの栄養成分表示(計算方法)について
更新日:令和7(2025)年4月17日
ページ番号:4822
メニューの栄養成分表示(計算方法)について
「健康ちば協力店」に登録申込する際に必要となる、メニューの「野菜量」や「食塩相当量」の計算方法についてご案内します。
野菜量や食塩相当量の計算に慣れてきたら、栄養成分の計算にもチャレンジしてみましょう。
- (初級編)野菜量の計算方法
- (中級編)食塩相当量の計算方法
- (上級編)栄養成分の計算方法
- (解説)料理の栄養成分の計算について
下準備
準備するもの
- メニューの食材(調味料を含む)、はかり、計量スプーン、筆記具、メモ用紙、電卓、日本食品標準成分表2020年版(八訂) (以下食品成分表)
 |
 |
 |
計算したい料理の1人前の食材料の重さをはかる
| 食材の皮や骨などの廃棄部分を取り除く。
|
  |
| ↓ |
| 料理のメニューごとに、1人前あたりの食材の使用量を、計算用紙(献立表)に記入する。
|
 |
1.(初級編)野菜量の計算方法
「下準備」で作成した献立表の中から、食品成分表で「野菜類」の欄に掲載されている食材をぬき出す。
野菜類の重さを合計すると、野菜量の計算が完成です。
- 野菜類に入らない食材(間違いやすいので注意)
だいず(豆類)※えだまめ・もやしは野菜類になります。
いも(いも類)
アボカド、うめ、オリーブ(果実類)
きのこ全般(きのこ類)
海藻全般(藻類) - 新しい野菜等、食品成分表に掲載されていない食材の分類については、各健康福祉センター(保健所)へご相談ください。
2.(中級編)食塩相当量の計算方法
「下準備」で作成した献立表の中から、すべての食材について『食塩相当量』を計算する。
- 食品成分表から、計算したい食材を探す。
- 「下準備」で作成した献立表に書いた食材の重さに、食品成分表に掲載されている『食塩相当量』をかけて計算する。
食品成分表に掲載されている『食塩相当量』は、各食材100グラム当たりの量です。
(例:塩鮭、可食部80グラムの場合)
塩鮭→魚介類→しろさけ【塩ざけ】食塩相当量は100グラム当たり1.8グラム
1.8グラム×80グラム÷100グラム=1.44グラム=約1.4グラム - 献立表のすべての食材について『食塩相当量』を計算して、献立表に記入する。
- 献立表に記入した『食塩相当量』を合計する。
- メニューの『食塩相当量』の計算が完成です。
3.(上級編)栄養成分の計算方法
「下準備」で作成した献立表の中から、すべての食材について『エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量』等の栄養成分を計算する。
- 食品成分表から、計算したい食材を探す。
- 「下準備」で作成した献立表に書いた食材の、重量あたりに含まれる『エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量』を、食品成分表を用いて計算する。
※食品成分表に掲載されている栄養成分は、各食材100グラム当たりの量です。
- 献立表のすべての食材について、各栄養成分を計算して、献立表に記入する。
- 献立表に記入した各栄養成分を合計する。
- メニューの栄養成分の計算が完成です。
- メニュー表等に、わかりやすく表示して、お客様にお知らせしましょう。
【飲食店内での表示場所の例(メニュー、店内の掲示物、卓上メモ等)】
 |
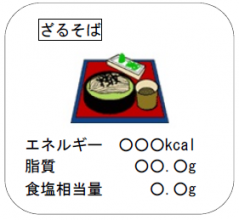 |
注意:お弁当や菓子等の一般消費者向け加工食品を販売する場合には、『食品表示法』により定められた方法でその食品の容器包装に栄養成分表示をすることが必要です。
(参考:千葉県ホームページ内)
「正しい食品の表示を」
「食品の栄養成分表示について」
(解説)料理の栄養成分の計算について
- 「日本食品標準成分表2020版(八訂)」が最新版です
- 食品は、下記の食品群ごとに、「あいうえお順」に掲載されています
- 穀類
- いも及びでん粉類
- 砂糖及び甘味類
- 豆類
- 種実類
- 野菜類
- 果実類
- きのこ類
- 藻類
- 魚介類
- 肉類
- 卵類
- 乳類
- 油脂類
- 菓子類
- し好飲料類
- 調味料及び香辛料類
- 調理済み流通食品類
- 栄養価は、可食部(皮や骨などの廃棄部分を除いた実際に食べる部分の重さ)100g当たりの数値で掲載されています
- 栄養成分(エネルギー、脂質、カルシウム、鉄など)ごとに表示単位および位どりは異なります
- 日本食品標準成分表は、書店等で市販されています。
また、内容については文部科学省のホームページ で無料で公開されているほか、食品成分データベースで検索することが可能です。
で無料で公開されているほか、食品成分データベースで検索することが可能です。
栄養成分の計算のポイント
栄養成分計算をしたい料理の献立表が作成が、もっとも重要な作業となります。
献立表作成のポイント
- 料理の食材はなるべく正確に計量する。
(特に注意するポイント)
皮や骨などの廃棄部分を除いた可食部の重さをはかる。
食塩やしょうゆ、みりん等の調味料の重さもはかる。
炒め油、つけダレ、ドレッシング、天盛の薬味も忘れやすいので注意して重さをはかる。
1人前ずつの重さが量れない料理の場合は、それぞれの材料の全体の重さを人数で割って、1人前当たりの重さを算出する。
揚げ物は、吸油率を参考として、使用した油の重さを算出する。 - 食材の種類や、部位も記入します
魚や肉の部位によりエネルギーや脂質の量、野菜の種類によるビタミンの含有量等、似た食材でも栄養成分が異なる。
なるべく、料理に使用する食材に近い食品を、食品成分表から探すことができるように献立表に記録しておく。
その他
不明な点は、各健康福祉センター(保健所)へご相談ください
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
