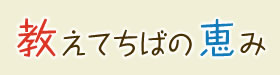ここから本文です。
更新日:令和7(2025)年6月13日
ページ番号:316983
ハム|旬鮮図鑑
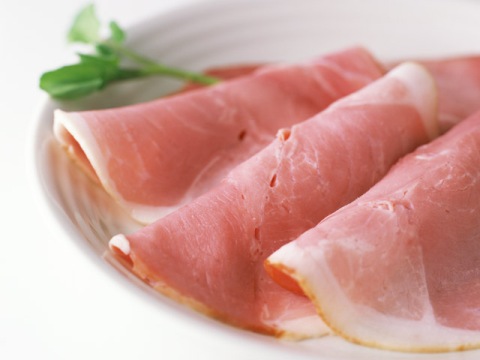
スライスされたハム
写真はイメージです
世界のハムの歴史
 ハムがいつ頃からどこで作られるようになったのかについては、よくわかっていないようです。
ハムがいつ頃からどこで作られるようになったのかについては、よくわかっていないようです。
家畜として豚が飼われるようになったのが紀元前4,000年とも7,000年ともいわれており、加工を伴うハムが作られるようになったのはそれ以降であることは明らかです。
ヨーロッパでは、豚の飼育は北方森林地帯において発達してきました。
日照時間が短く寒冷で土地のやせたこの地域では、穀物の生産性が低いため、秋になってナラの森に豚を放し、ドングリを食べさせて太らせ、それをと殺してハムやベーコンに加工してきた歴史があります。
また、このようにして保存性を高めることで、冷蔵設備のない時代の蛋白源として貴重な食材となっていました。
日本のハムの歴史
 日本のハムの発祥の地は長崎・出島といわれています。
日本のハムの発祥の地は長崎・出島といわれています。
記録として残されているものの中には、長崎市大浦の片岡伊右衛門が明治5年に長崎に来遊したアメリカ人のペンスンからハムの製法を伝授され、工場を建設して製造を開始したとされています。
また、明治7年に神奈川県戸塚でホテル業を営んでいたイギリス人ウイリアム・カーティスが牛・豚を飼育し、ハム・ベーコンを製造して横浜在留の外国人に販売していたとのことです。
この製法を会得して自ら研鑽した日本人が鎌倉地域のハム「鎌倉ハム」としてその名を残してきました。
写真は長崎市佐世保の風景で、イメージ写真です。
技術の伝承に関わった千葉県人
匝瑳郡東陽村(現横芝光町)出身の大木市蔵氏(明治29年生)は、横浜においてドイツ人マーチンヘルツ氏に技術を学び、横浜に大木ハムを起こしました。
大木氏は、その後、全国各地でハム・ソーセージの技術伝承に奔走され、日本の食肉加工技術の浸透に大いに貢献されました。
出典:増田和彦著「ソーセージ物語」
日本のハムの種類(部位との関係)
日本のハムの種類(部位との関係)
| ハムの種類 | 使用部位 |
|---|---|
| ショルダーハム | カタ肉 |
| ロースハム | ロース肉 |
| ベリーハム | バラ肉 |
| 骨付きハム、ボンレスハム | モモ肉 |
| ラックスハム | カタ肉、ロース肉、モモ肉 |
| プレスハム | 塩せきした畜肉等の肉塊に結着補強剤等つなぎを加えて混合し、ケーシング※に充てんしたもの |
ロースハムの製造過程
食肉を原料に使用していることから、原料から納品までの品質管理には特に注意が払われており、衛生管理、温度管理、細菌管理など全工程において、さまざまなチェックが行われています。
- 整形

原料肉のスジや脂肪などを除き、用途別に整形カットし、分類します。 - 塩せき
原料肉に塩、発色剤などを加えてしばらく冷蔵庫内で熟成します。 - 充てん
ケーシング(皮)に詰めて形を整えます。
ケーシングの分類
・可食性ケーシング:家畜の腸などを加工して塩蔵したコラーゲンケーシング
・不可食性ケーシング:セルロース系ケーシング、ポリ塩化ビニリデン系ケーシング(ロースハムやボンレスハムには非可食性ケーシングが使われる) - 乾燥燻製
煙でいぶします。これによって保存性を高め、外観にいい色と、いい香りをつけます。(燻煙しない場合もあります) - 蒸煮
燻煙だけでは十分な加熱ができないので、湯または蒸気で中心部まで十分加熱します。 - 冷却
直ちに急冷却して肉質を引き締めて、細菌が増えるのを防ぎます。 - スライス・包装
それぞれの商品別、用途別にスライスし、包装します。 - 検査
厳しい品質チェックを経て出荷されます。
ハムの保存期間と注意点

〔賞味期限〕→〔保存期間〕→〔腐敗〕
ハムは加熱殺菌が十分に行われていますので、かなりの期間はそのままの品質を保ちます。
その後、成分の劣化が少しずつ進みますが、賞味期限が経過しても十分に食べられます(自己責任)。そして、ついに食べられなくなる状態になるまでの期間を保存期間といいます。
保存期間は、外観の色、臭い、組織、ネトの発生などで判断してください。保存期間を過ぎた時点で「腐った」ことになります。
ハム保存期間
| ハムの種類 | 期限表示のために設定されている期間 冷蔵(0度から10度) |
開封後 冷蔵(0度から10度) |
|---|---|---|
| ロースハム・ボンレスハム(1本もの・真空包装) | 14日から70日 | 2日から7日 |
| プレスハム(1本もの・真空包装) | 30日から85日 | 2日から7日 |
| スライスハム(真空包装) | 7日から60日 | 2日から3日 |
| 生ハム(スライス・真空包装) | 14日から60日 | 2日から3日 |
ハムの保存上の注意点
- 開封前でも表示に従って所定の温度以下に保存します。
- 1本もののハムは、開封後の切り口部分が早く傷みますので、切り口にラップを張り付け、次に使用するときは切断面を少し切り落とせば開封前に近い状態で食べられます。
- 冷凍庫に保存すると、解凍時に水分が分離しておいしくなくなります。やむを得ず冷凍する場合は、1回分ずつ小分けにし、空気を入れないようぴったりと包み、解凍するときは冷蔵室でゆっくりと解凍してください。
出典:食肉加工品の知識(社団法人日本食肉協議会)
世界のハムの概要と呼び名
 英語・米語Ham(ハム)
英語・米語Ham(ハム)
ドイツSchinken(シンケン)
フランスJambon(ジャンボン)
イタリアProscuiutto(プロシュート)
スペインJamon(ハモン)
ハムの調理のポイント
 あまり手間をかけずに素材の持ち味を損ねない程度に調理すること
あまり手間をかけずに素材の持ち味を損ねない程度に調理すること
もともと塩分が含まれており、塩分を計算して調理すること
ハムをステーキにする場合は、脂肪が出きってしまうと旨味がなくなってしまうので、強火で手早く調理すること
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください