ここから本文です。
ホーム > 教育・文化・スポーツ > 歴史・文化 > 文化・文化財 > 文化遺産 > 彫刻・絵画・工芸品など > 石造物 > (南房総市)石造延命地蔵尊坐像
更新日:令和6(2024)年2月19日
ページ番号:6074
(南房総市)石造延命地蔵尊坐像
内容
- 市指定有形文化財(彫刻)(昭和55年1月1日指定)
- 住所:南房総市本織番場652の1(真言宗)日照山普門院
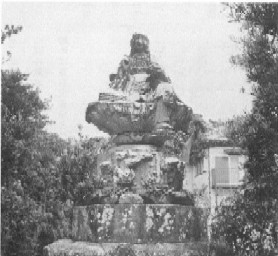 この地蔵尊像は、本織番場の普門院(新義真言宗)の入口に在る45センチ、横78センチ、高さ78センチの半跏思惟の石像で、台の高さは74センチである。「石巧・当村・武田産・秀治」の銘が刻まれている。
この地蔵尊像は、本織番場の普門院(新義真言宗)の入口に在る45センチ、横78センチ、高さ78センチの半跏思惟の石像で、台の高さは74センチである。「石巧・当村・武田産・秀治」の銘が刻まれている。
地蔵菩薩は、仏教で釈迦が入滅してから56億7000万年後に弥勒仏が出生するまでの無仏の間、この五濁の世に出現して六道の衆生を救済する菩薩であると言われ、末法思想が盛んになるにつれ広く信仰されて来た仏である。
作者「武田石翁」は、安房先賢偉人の一人で、木彫の「武志伊八」「後藤義光」と共に安房の生んだ偉大な彫刻家である。
石翁は、安永8年(1779)1月、本織宇戸の武田家に生まれ、名を周治と言い、字は是房、号を天然道人、天然斉などと称し晩年「石翁」と号した。石翁は、幼にして手工芸を好み殊に彫刻の才を備えており、寛政3年(1791)平郡元名村(鋸南町)の石工小滝勘蔵の弟子となり石匠の業を修めた。23歳の時望まれて師勘蔵の養嗣子となり、安政5年(1858)8月に80歳で没するまで彫刻活動を続けた。
石翁の彫刻は石にその材を求め、40歳以後の作品に見るべきものが多く、漢学者「嶺田楓江」は石翁の作品に大いに感歎し一詩を賦したと言われ、近くは石川淳の「諸国畸人伝」や「安房先賢偉人伝」にも詳述されている。
- 三芳村(現南房総市)内に残る代表的作品
- 十一面観音小立像………宝珠院(府中)
- 溝口八郎右衛門墓石……智蔵寺(山名)
- 大黒天像………………溝口重治(山名)
- 阿弥陀像………………神作秀雄(本織)
- 稲荷木像………………武田康治(本織)
- 唐獅子…………………出山貞司(上滝田)
出典・問い合わせ先
- 出典:「三芳村の文化財」
- 問い合わせ先:南房総市
 (旧三芳村が合併)
(旧三芳村が合併)
関連リンク
お問い合わせ
※内容については、お手数ですが「問い合わせ先」の各市町村へお問い合わせください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
