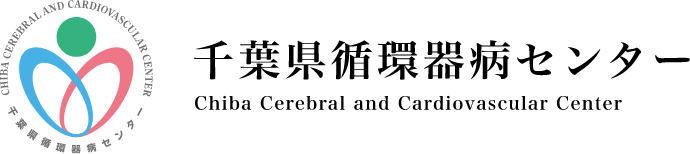成人先天性心疾患
成人先天性心疾患とは、生まれつきの心臓病(先天性心疾患)を持ち、15歳あるいは18歳以上の成人になった患者さんの事を指します。
先天性心疾患は、長生きができない病気と考えられてきましたが、近年の内科診断と外科治療の進歩により、多くの子どもの患者さんが成人となることが可能となりました。先天性心疾患の手術の多くは根治手術ではないため、成人となった術後の患者さんにも、継続的な長期間の経過観察が必要です。
日本では生産児の約1%が先天性心疾患として生まれ、そのうちの90%以上が成人します。従って、成人先天性心疾患の患者数は、今後ますます増加していきます。先天性心疾患といえば、1980年頃は子どもの病気でしたが、2000年頃には成人患者数と小児患者数は殆ど同数になりました。2020年代になって、成人患者数は小児患者数を遙かに凌駕しています。先天性心疾患は既に成人循環器疾患の1領域と考えられます。
成人先天性心疾患患者は、主に循環器科小児科医が継続して診療してきました。今のところ、循環器内科医のこの分野への関心は高くはありません。しかし、患者数の増加、加齢の進行、さらに後天性心疾患と同様に心不全や不整脈が問題となることが多いため、近い将来、この分野は循環器内科医の興味を引くことは疑いがありません。
小児の未手術チアノーゼ型先天性心疾患は減少していますが、成人では一定数が存在するため、系統的多臓器異常に対する医療が必要です。複雑型心疾患の術後の成人患者も増加しています。先天性心疾患の手術の多くは根治手術ではなく、合併症、残遺症、続発症などを伴います。そして、加齢に伴い、心機能の悪化、不整脈、心不全、突然死、再手術、感染性心内膜炎、妊娠・出産、高血圧、冠動脈異常、非心臓手術などによって、病態、罹病率、生命予後が修飾されます。
さらに、就業、保険、結婚、心理的社会的問題、喫煙など成人特有の問題も加わってきます。このため、成人先天性心疾患の患者さんの多くは、循環器小児科だけでなく、循環器内科、心臓血管外科、麻酔科、一般内科・外科、周産期科などを加えた、チームでの診療を必要とします。
成人先天性心疾患における当院成人先天性心疾患診療部の役割
当診療部は、成人先天性心疾患を専門とする経験豊かな医師を中心として、成人先天性心疾患の患者さんの総合的な診療を行うために、日本で初めて開設されました。成人先天性心疾患にみられる、不整脈、心不全、肺高血圧症、チアノーゼ合併症、妊娠等に対して、チーム医療を行える診療体制を備えました。また、成人となった小児期心疾患、例えば、川崎病後の冠動脈後遺症の患者さんの診療も行います。
現在は小児科・成人先天性心疾患診療部を縮小中のため、入院の受け入れを行っていません。心臓カテーテル検査や外科的手技、入院管理や夜間・休日の救急診療などが必要となる可能性のある患者さんは、連携病院に紹介させていただいています。
当院成人先天性心疾患診療部の学術的な役割
この分野は新しい分野であり、年々多くの新しい臨床研究が行われています。当院の成人先天性心疾患診療部は、国内外の多施設研究を企画、或いは参画し、講演、学会発表、論文発表などを広く行い、この分野の発展に貢献できるように努力しております。
これ以外に、
-
「日本成人先天性心疾患学会」事務局と協力しながら、以下の学会関連の諸活動を行っています。毎年行われる総会・学術集会の企画・運営に参加しています。 患者さんや若手医師の教育のための「成人先天性心疾患セミナー」の企画・運営に参加しています。
-
成人先天性心疾患に関する参考書の企画、執筆などの活動に参加しています。これまでに、医療関係者向け、研修医向け、患者さん向けの参考書や解説書が出版されています。
-
小児循環器疾患や成人先天性心疾患に関する学会発表、論文執筆、ガイドライン作成活動などに参加しています。
当院の成人先天性心疾患診療部は、成人先天性心疾患の診療だけではなく今後の成人先天性心疾患の診療の向上のために、臨床研究、結果発表、論文作成、教科書作成、患者さんに対する病気病態の伝達、さらに若手医師の教育の役割を担っていく予定です。