ここから本文です。
更新日:令和7(2025)年12月23日
ページ番号:723660
防災活動の優良事例
千葉県地域防災力向上知事表彰
令和7年度

自主防災活動の部
| 被表彰者 | 選定理由 |
|---|---|
| 鶴枝自治会長 連合会 (茂原市)
|
平成23年度から約2年間、研修会を実施して「鶴枝第二次避難所活動体制マニュアル」を作成し、平成25年度から現在に至るまで、10年以上にわたり鶴枝小学校区大震災避難訓練を実施している。 毎年度、3回程度の災害対策会議と研修会を行って、防災訓練の内容の具体化を図り、基本的な行動の他に、炊出しなど、年度ごとに異なる訓練を加え、災害対応能力の充実を図りながらも、単位自治会毎に避難所における役割(総務班以下7個班)を固定化することで、各班の対応能力の維持向上に努めている。また、地区内に所在する特別養護老人ホームも訓練に参加し、要介護者の対応を想定した訓練も行っている。 さらに、茂原市防災対策課、避難所担当職員、地域在住市議会議員、民生委員、消防団、千葉県災害対策コーディネーター茂原、郵便局等の関係団体と連携した訓練を行い、地域防災力の向上に寄与している。 |
| 数馬区防災会 (富津市) |
平成22年度から10年以上にわたり、毎年、防災に関する訓練又は、研修を実施している。富津市防災安全課、富津市消防本部・富津市消防団や数馬区防災会が活動する地域の学校と連携した合同訓練も行い、地域の高校生が小学生と一緒に避難するなど、災害対応能力の向上を図っている。令和6年12月には、平日昼間の役員がいない状況において、被災状況の把握及び安否確認をする訓練を実施し、平日昼間の課題検索などにも務めている。 また、災害時に各地区で一時的に集まる場所を記した数馬区防災会独自の広報紙「よりどころ」を作成し、平時から災害を意識した活動がとれるよう広報活動も行っている。 さらに、隣接する自治会に訓練の参加を呼びかけ、指定避難所への避難訓練や安否確認訓練を合同で行っており、訓練の指導役として、地域全体で防災活動に取り組んでいる。 |
学校における防災活動の部
| 被表彰者 | 選定理由 |
|---|---|
| 千葉県立旭農業 高等学校 (旭市) |
学校が所在する旭市は、東日本大震災において、津波により甚大な被害を受けたことから、農業の知識や技術を活かし復興の一助となるべく活動を開始した。生徒会役員が中心となり、学校圃場で栽培、収穫、袋詰めした米に、生徒が書いたメッセージカードを添えて、災害公営住宅に居住する方々へ手渡しで配付する活動を続けている。生徒たちが被災された方に援助活動を行うことで「思いやりのある豊かな心」や「社会奉仕」の精神の涵養を図っている。 また、海岸沿いの県所有地2900平方メートルに、平成31年からの4年間で防災林植樹を行い、5年目以降は全校生徒で下草刈りの管理作業やごみ拾いを続け、防災の重要性を知る機会としているほか、防災林の再生活動と同日に校内で津波に対する避難訓練を行い、日頃から防災意識をもてるように工夫している。 |
事業所等における防災活動の部
| 被表彰者 | 選定理由 |
|---|---|
| 株式会社合同資源 (長生村) |
社内における防災研修及び訓練のほか、東日本大震災以降、長生村の地震津波避難訓練にも10年以上に渡り継続的に参加し、防災活動に社員を導入している。 また、長生村と災害協定を締結し、平成25年には緊急避難場所として施設を提供しているほか、近年、長生村や近隣自治体等に土嚢やブルーシート等、防災に係る物品の寄附を行っている。令和4年建設の新社屋には、地域住民避難用の備蓄倉庫、備蓄物資、外付け避難階段、多目的室などを備え、地域の防災力向上に寄与している。 さらに、地域の自主防災組織との連携を特に強化しており、施設の開放のみならず、備蓄物資の保管や提供等も行っている。当該企業が長生村の地震津波避難訓練に参加する前から取組を進めていたこともあり、本地域の住民は長生村主催の避難訓練の際にも、長生村指定の避難場所ではなく、自主的に当該企業の避難場所に集まるとともに、セミナーや体験会を開催する等、行政(公助)との連携を図りつつ、自助・共助の育成を進めている。 |
令和6年度

自主防災活動の部
| 被表彰者 | 選定理由 |
|---|---|
| 公益社団法人 災害ボランティアネットワーク・市原 (市原市) |
平成16年に市原市内のセーフティリーダー(SL)が組織化して活動し、平成26年3月に公益社団法人の認定を受けた。平時・災害時に関わらず、ボランティアの基本理念に沿い、地域との連携・協調及び行政との協働を推進している。 東日本大震災の際は、救援物資の受付や避難者の住居斡旋業務の支援などを行ったほか、令和元年房総半島台風等一連の災害においては、避難所運営や災害ボランティアセンターの運営、ボランティア活動、募金活動等に従事した。 平時には、市原市はもちろん、県内多数の市町村における防災講座や防災訓練への協力、イベント等における防災啓発活動等を行っているほか、図上演習等を通じた会員のスキルアップにも取り組んでいる。 また、県内市町村に限らず、県内各種団体、小中学校等々における防災講座や体験指導等への講師派遣を行い、地域防災力の向上に寄与している。 |
| 白金小学校区合同防災訓練実行委員会 (市原市) |
昭和60年頃、学区内における町会の成立に伴い、地域の自主的な取組として、各町会と学校が合同で、災害発生を想定し、住民が協力して無事に避難することを目的とした防災訓練を毎年実施している(コロナ禍により令和2年から4年は中止)。 地震発生を想定し、地域住民は最寄りの公園に1次避難し、2次避難として学校に集まり、東日本大震災後は津波避難として、校舎内の指定された教室まで移動する訓練が行われており、地域住民の地震発生時の動きを定着させている。 住民が無事に避難するための訓練と併せ、市原消防局五井消防署の協力により、運動場や体育館で煙道訓練、消火訓練、起震車体験、心肺蘇生、消防車車両見学なども行い、地域防災力の向上に寄与している。 地域の各町会(12町会)と学校のほか、消防団第8分団、市原市消防局五井消防署、市原市役所危機管理課の協力を得て、地域の多様な主体が連携した、地域の一大行事として行われている。 |
学校における防災活動の部
| 被表彰者 | 選定理由 |
|---|---|
| 市川市立塩浜学園 (市川市) |
東日本大震災で塩浜地区が液状化の被害を受けたことから、防災の必要性を強く感じ、小中一貫校として開校した平成27年度より、特別な教科「塩浜ふるさと防災科」を創設した。「塩浜ふるさと防災科」での学習を通じ、正しい防災知識を身につけ、行動できる児童生徒を育成している。 また、令和元年度には、学校安全総合支援事業の拠点校となり、 学校と地域が一体となって取組むモデルとして実践を行った。 「塩浜ふるさと防災科」では、町づくりや防災をテーマとしたゼミ活動として、地域安全マップ作成、普通救命講習の受講、生徒企画の防災訓練などを実施し、地域や児童生徒に向けて発表活動を行っている。また、東日本大震災の被災経験を持つ地域住民から話を聞き、地域の防災倉庫を見学したり、地元企業の防災士資格保有者から災害時の自助・共助について得た知識を下学年の児童生徒に伝えたりして、学校全体で防災教育に取組んでいる。以上の活動について、企画書や報告書を作成し、成果と課題の把握・取組の改善を図っている。 |
| 千葉県立 館山総合高等学校(館山市) |
「防災マニュアル~生き抜くための6か条~」を考案し、駅や市役所等での配布を行ったほか、「防災すごろく」を考案し、地域の防災訓練等で子供や高齢者等と一緒に実施するなど、市民の防災意識の向上を図っている。 令和元年房総半島台風の際は、被害の大きかった地区を訪問し、生徒から主体的に支援活動を申し出て、災害支援物資の配付やエコノミークラス症候群を予防するマッサージ講座を開催したほか、 被害状況や被災者の声を消防や行政に連絡して被害状況の把握に貢献した。 また、平成26年から、館山市内各地区の防災訓練や消防団のイベントに継続して参加し、地域住民と共に炊き出しやバケツリレー、消火訓練に参加するなど、地域防災力の向上に貢献している。 さらに、防災・減災の取組を高等学校家庭クラブ研究発表大会で継続して発表しており、令和6年は関東ブロック代表として全国大会で発表を行った。 |
令和5年度

自主防災活動の部
| 被表彰者 | 選定理由 | |
|---|---|---|
| 千葉県災害対策 コーディネーター茂原(茂原市) |
|
学校における防災活動の部
| 被表彰者 | 選定理由 | |
|---|---|---|
|
平成26年から有志の生徒が活動を行っていたが、災害時、長生村に貢献できる中学生の育成を目指し、令和3年6月に「防災部」を設立。 学校が避難所となった場合を想定したワークショップのほか、令和5年2月のトルコ・シリア地震に対しては、村内の小学校の防災クラブと連携し、募金活動を行った。 また、自衛隊と連携した活動として、防災に必要な考え方などに関する講義の受講、人命救助の際に使う道具の使用体験を行ったほか、令和元年10月の大雨災害により氾濫した一宮川の治水工事現場を継続的に見学している。 さらに、長生村避難訓練に継続して参加し、避難所における避難者の受入れや誘導訓練を行うなど、地域住民との連携を強めているほか、長生村土建組合、長生村役場との土嚢づくり体験や、双葉電子工業長生工場にて、被災時のドローン活用技術を学ぶなど、地域と連携した活動を行っている。 |
令和4年度

自主防災活動の部
| 被表彰者 | 選定理由 |
|---|---|
| 和良比小避難所運営委員会(四街道市) | 東日本大震災を機に、平成26年に近隣8区・自治会がまとまり設立。市が示す避難所運営マニュアルを基に独自のマニュアルを作成し、それを実践するための避難所開設運営訓練を実施することで、「共助」意識の向上を図っている。訓練にあたっては、新型コロナウイルス感染症の感染状況等に対応した実施 要領を定め実施するなど、工夫を凝らしている。 |
学校における防災活動の部
| 被表彰者 | 選定理由 |
|---|---|
| 袖ケ浦市立長浦中学校 (袖ケ浦市) |
平成25年に県教育委員会事業「命の大切さを考える防災教育公開事業」実践校として指定されて以来、年4回の避難訓練を実施している。開始時間を指定しない訓練や、消防署と連携して消火体験等様々な体験を実施するなど、実践的な取組を実施している。また、近隣の小学校・自治会連合役員と連携し、津波を想定した避難訓練を継続して実施している。 |
事業所等における防災活動の部
| 被表彰者 | 選定理由 |
|---|---|
| 千葉科学大学学生消防隊 (銚子市) |
平成17年の設立以降、実践操法大会や出初式へ参加するとともに運営の協力も行い、市の消防団と常時連携を図っている。また、隊員自らが企画運営し、市の消防本部や海上保安部などの外部機関と連携・協力して、大学祭において防災訓練を毎年実施している。 市や地域団体が行う防災訓練や住民参加の各種行事などに積極的に参加し、雑踏警備や交通整理など学生消防隊ならではの活動を行っているほか、市や保育園、小中学校とも連携して防災啓発活動を積極的に実施している。 また、災害時には被災地でのボランティア活動に従事するなど、地域防災活動に貢献している。 |
令和3年度

自主防災活動の部
| 被表彰者 | 選定理由 |
|---|---|
| 尼ケ台南部自主防災会 (長生村) |
平成20年に地震その他の災害による人命の安全確保、被害の防止及び軽減を図ることを目的として設立され、防災視察研修の主催や普通救命講習会の企画、村主催の防災訓練に毎年参加し炊き出し訓練等を実施するなど、継続して精力的に活動し、地域住民相互による「共助」精神向上を図っている。 また、地元の社会福祉施設と連携し、施設の避難訓練や勉強会への参加、利用者の避難支援を実施するなど地域社会と深く連携した活動により、地域防災力の 向上に取り組んでいる。 |
学校における防災活動の部
| 被表彰者 | 選定理由 |
|---|---|
| 印西市立原山中学校 (印西市) |
平成22年より、市主催の総合防災訓練に生徒や職員が毎年参加し、行政や地域住民、外国人など多様な参加者との訓練を通じて、災害時の実践的な防災対策を学んでいる。 また、開校当初から地域連携に熱心に取り組み、特に原山中学校区三校連絡会や「おやじの会」によるパトロールや、生徒会等主催による古紙回収の取組においては、災害時における地域の危険箇所等の実情把握が行われるとともに、地域住民との交流により災害時に協力し合う関係の構築がなされている。 |
令和2年度

自主防災活動の部
| 被表彰者 | 選定理由 |
|---|---|
| 幕張ベイタウン自治会連合会防災委員会(千葉市) |
平成9年に幕張ベイタウン自治会連合会の防災・防犯委員会として発足し、令和2年現在では30団体、6807世帯にも及ぶ大規模な自主防災組織として活動。街区を超えて協力し合う防災体制(避難所の開設・運営方法の確立、物資配給・情報連絡体制のルール作りなど)を構築し、平成15年以降、用途別の防災マニュアルの作成・改訂を行っている。平成25年度からは、関係団体、行政機関等と連携したイベント(「防災そなえパークの日」、「九都県市合同防災訓練」)や、地域の小中学校と連携した避難所開設訓練を実施している。 |
| 大井自主防災かわせみ(南房総市) |
東日本大震災の支援活動をきっかけに、平成25年に設立。「日常的な顔の見える関係づくり」を基本に防災活動を行っており、大井区内における地震等での長期停電や道路陥没による孤立化を想定した備品整備と訓練を実施している。「区民の安全・安心」をテーマにした年1回の開催イベントを通じて、備品の格納場所・使用方法などを確認している。また、災害発生時には、区内の関係する組織や施設・大学等と連携して活動している。 令和元年の台風第15号・19号の際には、ドローンによる被害状況確認を行ったほか、停電・断水という中で、発電機・通信機器(無線やWi-Fi等)を駆使して各家庭での生活支援活動を展開するなど、区の中核として活動した。 |
学校における防災活動の部
| 被表彰者 | 選定理由 |
|---|---|
| 流山市立東部中学校(流山市) |
災害時における危険の認識や、日常的な備えを行うとともに、自らの命を守り抜くため「主体的に行動をする態度」の育成を目的に、年間を通した防災教育を実施。 平成25年度から、東部地区自治会連合協議会をはじめとした24の自治会や社会福祉協議会などと「地域合同防災訓練」を継続的に実施している。 また、訓練では、仮設ベッドや間仕切りの組立てなどの体験や、総合的な学習時間における防災教育の発表を実施し、学校と地域との連携を図り、地域社会の活性化につなげている。 |
事業所等における防災活動の部
| 被表彰者 | 選定理由 |
|---|---|
| 丸高石油株式会社(館山市/石油事業) |
災害時の給油にとどまらず、給水、炊き出し、人命救助、食料集積場など地域に役立つ公益的な機能を持つ「防災ステーション」(ガソリンスタンド)を平成20年に整備。ステーションには、太陽光発電システムによる停電時の給油、炊き出し用のガス供給設備やソーラーLED照明灯、耐震貯水槽などを完備。平成21年には災害時のサポート拠点として、館山市と「被災者支援に関する協定」を締結した。 また、平成29年には、警察、消防、自衛隊など関係機関と連携し、自社の事業継続計画(BCP)に基づく災害対応訓練を実施した。 令和元年の台風第15号の際には、停電のなか、大型発電機を動かして給油を再開し、市民生活の維持に大きく貢献した。 |
令和元年度

自主防災活動の部
| 被表彰者 | 選定理由 |
|---|---|
| パークグランディエデナ自主防災会(習志野市) |
災害時に独自の災害対策本部を設置し、集合住宅に特化した安否確認方法を各棟で実施。安否情報を災害対策本部に集約し、行政機関に報告する仕組みが確立されており、4棟一体の共助体制が構築されている。
また、集合住宅4棟からなる当該団地の特性を生かして作成した「防災マニュアル」を全戸に配布し、災害時の活動体制に役立てている。
|
学校における防災活動の部
| 被表彰者 | 選定理由 |
|---|---|
| 船橋市立湊中学校(船橋市) |
平成23年3月11日の「東日本大震災」で校庭が液状化し、校舎の一部が損壊した経験を生かし、「防災教育」について地域住民と協議を続けている。
新校舎が平成27年5月に完成し、翌年に一時避難施設として指定され、地域住民・市職員・学校職員・生徒と垣根を超えた津波避難訓練を継続的に行っている。
|
事業所等における防災活動の部
| 被表彰者 | 選定理由 |
|---|---|
| ガラスリソーシング株式会社(銚子市/廃棄物処理業) |
東日本大震災を契機に、地域住民や社員を守るため災害用備蓄倉庫の建設に向け活動を開始し、平成28年3月に災害用備蓄倉庫「蔵」を建設、翌年8月には災害時警察業務に必要な要請に対し、即対応することが可能な施設「危機管理棟」を建設し、「災害時における防災備蓄物資の提携協力及び施設の使用並びに災害応急対策業務に関する協定書を銚子警察署と締結した。 また、建設した施設を実用性の高いものとするべく、社員・地域住民をはじめとする市民・日本赤十字社千葉県支部等が参加した「災害時炊き出し訓練」を実施した。 |
平成30年度

自主防災活動の部
| 被表彰者 | 選定理由 |
|---|---|
| 那古地区連合町内会 | 海岸線を有しながらも自主防災組織が結成されていない等の問題改善のため、「那古地区住民全員が自分の命は自分で守り、生き延びるために町内会での助け合いが出来ること」を目標に、18の町内会からなる地区全体で避難訓練を実施するなど自主防災活動の活性化を図っている。 |
学校における防災活動の部
| 被表彰者 | 選定理由 |
|---|---|
| 香取市立香取中学校 | 避難訓練において、学校職員及び生徒には事前通知せずに、通常の避難経路の通行不可、負傷者の発生などを行うことにより、不測の事態への対処等、防災力の向上に向けた取組を行っている。 |
事業所等における防災活動の部
| 被表彰者 | 選定理由 |
|---|---|
| 双葉電子工業株式会社 特設消防隊 (茂原市/製造業) |
新入社員教育の中での消防隊規律訓練の実施や、新入社員を対象とした仮入隊制度を制定するなど、社員の防災意識の向上に努めている。 また、社内の消火活動だけでなく、近隣の火災などにも出動し、地域防火活動にも貢献している。 |
平成29年度

自主防災活動の部
| 被表彰者 | 選定理由 |
|---|---|
| 中金杉自治会防災部(松戸市) | 3~6軒毎に共助班を組織、班長を中心に見守り活動と安否確認を実施する。毎年独自の調査を行い、避難行動要支援者を把握している。「災害時支援協力者」として医師、看護師など様々な人材を登録する制度を行う。 |
| 津田沼ハイライズ自主防災会(習志野市) | 15階の高層マンションで、階層ごとの安否確認、シェイクアウト訓練、はしご車による高層階からの救出訓練など年2回の訓練を実施する。防災ペーパーを毎月発行し住民の意識啓発に力を入れる。 |
| 津宮十一区自主防災会(香取市) | 会長と役員がトランシーバーを持ち、震度4以上の地震や台風発生時には町内84世帯の安否確認と根本川の警戒を行う体制を取る。津宮区の防災モデル地区として近隣地域を巻込み総合防災訓練を行っている。 |
学校における防災活動の部
| 被表彰者 | 選定理由 |
|---|---|
| 佐倉市立根郷小学校 | 学期に1回の避難訓練の他、毎月1回のシェイクアウト訓練と頻繁に訓練を行い、適切な避難行動を身につけさせている。地域の有志を「地域ボランティア」として登録し、避難訓練・見守り活動・防災マップ作成などに協力。 |
事業所等における防災活動の部
| 被表彰者 | 選定理由 |
|---|---|
| 千葉オイレッシュ株式会社(君津市/産業廃棄物処理業) | 社員の消防団活動を奨励、社員の2割強が消防団活動に従事、業務中の消防団活動は勤務扱いとし活動を支援している。地元町会の自主防災組織設立に協力し、立上げには地域防災倉庫と備品を寄贈、防災訓練にも協力する。 |
平成28年度

自主防災活動の部
| 被表彰者 | 選定理由 |
|---|---|
| 妙楽寺区自主防災組織(睦沢町) | 広域の山間部に住居が点在する地域性から、従前から、班ごとに統括者が定められ緊密な連絡体制を取っていたが、さらにアマチュア無線に詳しい住民で組織内に無線運営管理委員会を設置、災害時に班ごとに無線で連絡調整を行うこととし、毎月無線を用いた安否確認訓練を行っている。 |
学校における防災活動の部
| 被表彰者 | 選定理由 |
|---|---|
| 御宿町立御宿小学校 | 1年生は水色のすずらんテープで作った津波模型で5mの津波を体感し、「すぐにげる」「ひとりでもにげる」「たかいところへにげる」の3つの約束を覚えるなど、6学年それぞれ発達段階に応じたきめ細かな津波防災授業を実施。また、様々な時間帯での抜打ち避難訓練など、多様で実践的な避難訓練を行っている。 |
| 県立東金特別支援学校 | 防災教育を教育課程に位置付け、地域住民を巻き込み、防災ウォークラリーや防災グッズ探しゲームなど、様々な防災活動を実施。また、児童生徒会が「あたりまえ体操」の替え歌で、振付つきの防災ソング「あたりまえ防災」を作成し、県内外の防災教育実践校の模範的な取組みとなっている。 |
事業所等における防災活動の部
| 被表彰者 | 選定理由 |
|---|---|
| 株式会社風間建設工業所(船橋市/建設業) |
古くから除雪対策に力を入れ、降雪時には地域を巻込み活躍している。地域住民を招いての餅つき大会の際には、重機による瓦礫撤去やバールでの障害物撤去の演習などの防災啓発を行う。資材センターは災害時に地域住民への避難所になることを想定し、自家発電井戸や食料備蓄を実施している。 |
平成27年度
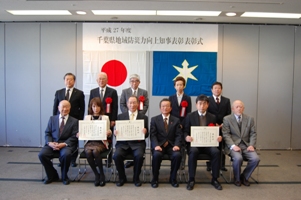
自主防災活動の部
| 被表彰者 | 選定理由 |
|---|---|
| 西山町会防災会(柏市) | 高齢者の多い地域性から、徹底した安否確認訓練を実施している。大規模災害を想定し、住民に事前に被害状況などは知らせずに、町会全世帯を35の班に分け「向こう三軒両隣」での安否確認を行い、確認率99.9%の精度が高い訓練を実現している。また、同会が中心となって近隣町会や学校と連携した避難所運営訓練も毎年開催し、地域の防災力の向上に貢献している。 |
学校における防災活動の部
| 被表彰者 | 選定理由 |
|---|---|
| 東庄町立神代小学校 | 毎年作成する防災計画に基づき、地震や火災など年4回の多様な避難訓練を実施している。特に家族への引き渡し訓練は長年継続的に実施しており、保護者の協力のもと、100%に近い保護者参加率となっている。また、学区を児童が自らの足で歩き危険箇所を把握する「学区の安全マップづくり」を実施、児童の防災意識の向上を図っている。 |
事業所等における防災活動の部
| 被表彰者 | 選定理由 |
|---|---|
| 本田土木工業株式会社(習志野市/建設業) |
地域の自主防災組織と連携しての防災活動に取り組んでおり、地域のための防災倉庫を自社に設置して資機材を整備するとともに、災害時には自社重機を提供することとして、平時から地域の防災訓練に参加している。また東日本大震災時には、地域の液状化による道路陥没を、自社重機によりボランティアで修繕し、避難経路の早期復旧に貢献した。 |
平成26年度

自主防災活動の部
| 被表彰者 | 選定理由 |
|---|---|
| 吹上苑町会自主防災会(習志野市) |
「地道」と「継続」をモットーに、住民の防災意識の向上や多くの住民を巻き込んだ啓発活動に尽力している。また、町会の「吹上苑町会おたすけ隊」と密に連携し、要配慮者世帯を定期的に巡回することで、全世帯の避難行動要支援者の最新情報を把握する等、要支援者対策に積極的に取り組んでいる。 |
| 本一町会自主防災部(習志野市) |
町内の18の通りごとに、共助の核となる「防災協力員」を募り、向う3軒両隣を基本単位とした安否確認を行うなど、町内全体の安全確保に努めている。また、小学校区内の約30の自主防災組織に呼びかけ、連絡会を発足し、校区の防災リーダー研修会等の実施にも積極的に取り組んでいる。 |
学校における防災活動の部
| 被表彰者 | 選定理由 |
|---|---|
| 成田市立向台小学校 | 子どもたちを取り巻く危険は様々であるとの認識のもと、毎年度、安全指導計画を作成している。避難訓練は日程を分けて、地震避難訓練・児童引き渡し訓練等を実施している他、竜巻を想定した訓練も実施する等、子どもたちが自ら危険を予測し回避出来る能力を身につける教育に積極的に取り組んでいる。 |
| 長生村立一松小学校 | 「地震イコール津波・即避難」の認識を高めるとともに、学年ごとに異なるテーマの防災授業を行い、発達段階に応じた取組みを行うことで適切な判断力の向上を図っている。また、村合同避難訓練に参加した児童が、防災集会において発表する取組を行う等地域と連携した防災教育に積極的に取り組んでいる。 |
平成25年度

自主防災活動の部
| 被表彰者 | 選定理由 |
|---|---|
| 中の島自主防災会(茂原市) |
平成元年及び平成8年に大規模な水害に襲われたことを踏まえ、災害時における要援護者支援対策等に取り組み、避難支援要綱や避難支援体制マニュアルを作成するとともに、避難模擬訓練等を積極的に実施している。 |
| 本大久保ホームタウン自治会自主防災会(習志野市) |
自治会役員とは別立ての公募による専任の防災委員からなる自主防災会を立ち上げ、組織の強化を図っている。 また、災害発生時に防災センターを自治会館に設置するとともに、簡易無線機や発電機を確保するなど、実践的な自主防災体制の構築に積極的に取り組んでいる。 |
学校における防災活動の部
| 被表彰者 | 選定理由 |
|---|---|
| 千葉県立市川工業高等学校 | 平成15年度から、建築科生徒の実習と課題研究のカリキュラムにおいて、地域の木造住宅に関する耐震構造の現状調査や耐震診断などを実施するとともに、自治会や大学等と連携した活動を行うなど、地域と連携した防災教育に積極的に取り組んでいる。 |
平成24年度

自主防災活動の部
| 被表彰者 | 選定理由 |
|---|---|
| 生実町防災会(千葉市) | 独自の広報スピーカーの設置により、防災行政無線不便地区の解消に貢献するとともに、地域住民に対する情報伝達体制を確立し、災害に対する備えが強化されている。 |
| 美田自治会(流山市) | 要援護者1人に対し4人の支援者を配置する避難体制の構築や避難所開設・運営訓練を行うなどのほか、防犯・防災フェスティバルを開催し、防災意識の向上に貢献した。 |
学校における防災活動の部
| 被表彰者 | 選定理由 |
|---|---|
| 旭市立飯岡小学校 | 東日本大震災での被災経験や避難所対応等の実体験を生かした実践的な防災教育を、各教科・領域に取り入れ、児童の自助、共助力の向上に生かしている。 |
| 南房総市立三芳中学校 | 学校独自の「防災マニュアルブック」の活用により自助・共助の育成を図るとともに、消防署の協力による防災訓練を実施するなど、実践的な取組を行っている。 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

